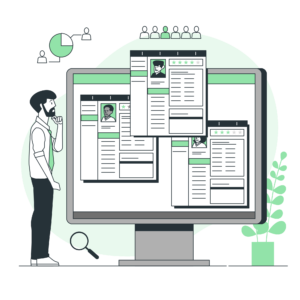個人事業主の書類保存期間ガイド!確定申告・帳簿・領収書・請求書等は何年保管?
こんにちは。
福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です。
「確定申告が終わった!でも、この大量の書類、いつまで保管すればいいの?」
「領収書や請求書、捨ててしまっても大丈夫?」
個人事業主として活動していると、日々たくさんの書類が発生しますよね。
確定申告が終わっても、これらの書類を適切に保管しておくことは、法律で定められた義務であり、ご自身の事業を守るためにも非常に重要です。
この記事では、個人事業主が保管すべき書類の種類とその正しい保存期間について、青色申告・白色申告の違いや消費税のポイントも踏まえながら、解説します。
この記事を読めば、書類整理の悩みがスッキリ解消し、安心して事業に集中できるようになります!
なお、法人の書類保存期間については下記の記事に記載しています。適宜ご参照いただけますと幸いです。
マインドマップ
当記事の内容をマインドマップにてまとめました。
適宜ご参照いただけますと幸いです。
なぜ?個人事業主が書類を保存するべき4つの理由
面倒に感じる書類の保存ですが、それにはちゃんとした理由があります。
- 正確な確定申告のため: 過去の取引記録は、次年度以降の正確な申告に役立ちます。
- 税務調査への対応のため: 税務署から問い合わせや調査があった際に、帳簿や領収書などがなければ、経費として認められなかったり、追徴課税を受けたりする可能性があります。書類は正当性を証明する重要な証拠です。
- 経営状況の把握・分析のため: 過去の売上や経費のデータは、経営判断や資金繰り改善のための貴重な資料となります。
- 法律で義務付けられているため: 所得税法や消費税法で、帳簿書類の保存が義務付けられています。違反するとペナルティが課されることもあります。
【所得税】の取り扱いについて
【結論】書類の保存期間は原則「7年」と「5年」!
まず結論からお伝えすると、個人事業主が保存すべき書類の期間は、主に以下の2パターンです。
- 原則7年保存
- 原則5年保存
以下で、書類の種類ごとに詳しく見ていきましょう。
保存が必要な帳簿・書類と保存期間(青色申告者の場合)
青色申告をしている個人事業主は、原則として7年間の保存義務が課されます(一部5年のものもあります)。
青色申告者が保存すべき主な帳簿・書類とその保存期間は次のとおりです。
| 書類の種類 | 具体例 | 保存期間 | 根拠条文(主なもの) |
| 帳簿(法定帳簿) | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年間 | ・所得税法 第148条第1項、所得税法施行規則 第63条第1項第1号 ・これらの帳簿は、その閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間保存(所得税法施行規則 第63条第4項) |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年間 | ・所得税法施行規則 第63条第1項第2号 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収書、預金通帳、小切手控、借用証など | 7年間(※例外あり:前々年所得300万円以下の場合5年) | ・所得税法施行規則 第63条第1項第3号 |
| その他の取引書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年間 | ・所得税法施行規則 第63条第1項 |
※上記の「現金預金取引等関係書類」について、青色申告者でもその年の前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合は、保存期間が5年になります。(所得税法施行規則 第63条第2項)
保存が必要な帳簿・書類と保存期間(白色申告者の場合)
白色申告の場合も、青色申告ほど詳細な帳簿は要求されないものの帳簿保存義務は存在し、保存期間は原則5年間です。
ただし一部は7年保存が求められます。
白色申告者が保存すべき帳簿・書類とその保存期間は次のとおりです。
| 書類の種類 | 具体例 | 保存期間 | 根拠条文(主なもの) |
| 帳簿(法定帳簿) | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 【参考】国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について | 7年間 | ・所得税法 第232条、所得税法施行規則 第102条第4項 ・これらの帳簿は、その閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間保存(所得税法施行規則 第102条第4項) |
| 帳簿(任意帳簿) | 業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年間 | ・所得税法施行規則 第102条第4項 |
| 決算関係書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年間 | ・所得税法施行規則 第102条第4項 |
| その他の取引書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、領収書、送り状など | 5年間 | ・所得税法施行規則 第102条第4項 |
【早わかり表】青色申告・白色申告の書類保存期間まとめ
| 書類の種類 | 青色申告の保存期間 | 白色申告の保存期間 |
| 帳簿(法定帳簿) | 7年 | 7年 |
| 決算関係書類 | 7年 | 5年 |
| 領収書・預金通帳など(現金預金取引等関係書類) | 7年 (※前々年所得300万円以下は5年) | 5年 |
| 請求書・見積書など(その他の書類) | 5年 | 5年 |
いつから数える?保存期間の「起算日」
これらの保存期間は、その年の確定申告期限の翌日から数え始めます。
例えば、2024年分(令和6年分)の確定申告期限は2025年3月17日なので、起算日は2025年3月18日となります。
- 7年保存: 2025年3月18日 ~ 2032年3月17日まで
- 5年保存: 2025年3月18日 ~ 2030年3月17日まで
【消費税】課税事業者の取り扱いについて
消費税の課税事業者(インボイス発行事業者を含む)は、所得税法とは別に、消費税法で定められた書類の保存義務があります。
仕入税額控除の適用には基本的に「7年保存」
消費税の申告で、仕入れにかかった消費税を差し引く「仕入税額控除」の適用を受けるためには、以下の書類を7年間保存する必要があります(消費税法施行令第50条)。
- 帳簿: 課税仕入れ等の事実を記載した帳簿
- 請求書・領収書等: インボイス制度開始後は、適格請求書(インボイス)やそれに類する書類
免税事業者の場合は、消費税の申告義務がないため、消費税法に基づく保存義務はありません(所得税法上の保存義務はあります)。
【参考】国税庁 タックスアンサーNo.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
インボイス発行事業者が交付する請求書も「7年保存」
インボイス発行事業者が取引先に「適格請求書」を交付する際に、その「写し」も7年間保存する必要があるので注意です!
消費税関係書類の「起算日」は所得税と違う!
注意点として、消費税関係書類の保存期間の起算日は、所得税とは異なります。
課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から数えます(消費税法施行令第50条)。
例えば、個人事業主で課税期間が1月1日~12月31日の場合、2024年分の課税期間の末日は2024年12月31日です。
その翌日から2ヶ月後は2025年3月1日(※)となるため、この日が起算日です。
- 7年保存: 2025年3月1日 ~ 2032年2月28日まで
所得税と消費税で起算日が異なるため、迷ったら長い方の期間(所得税基準の確定申告期限翌日から7年)に合わせて保存しておくのが安全です。
まとめ:個人事業主の書類保存はルールを守って確実に!
今回は、個人事業主の書類保存期間について解説しました。最後にポイントをまとめます。
- 基本の保存期間: 7年または5年(書類の種類、青色/白色申告で異なる)
- 消費税課税事業者: 仕入税額控除関連は7年、請求書の写しも7年
- 起算日: 所得税は「確定申告期限の翌日」、消費税は「課税期間末日の翌日から2ヶ月後」
書類の保存は、法律上の義務であると同時に、ご自身の事業を守り、発展させるための重要な業務です。
ルールを正しく理解し、日頃から整理・保管を習慣づけましょう。
投稿者プロフィール

-
久留米市の若手公認会計士・税理士です!
freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。
創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。
最新の投稿
 仕事の考え方や価値観2026年1月14日自分らしく生きたい!!情報過多の時代に必要なマインドセット
仕事の考え方や価値観2026年1月14日自分らしく生きたい!!情報過多の時代に必要なマインドセット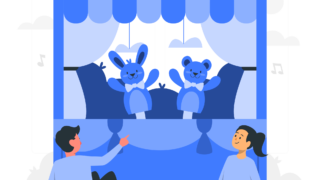 法人税2026年1月8日税務調査で狙われる「交際費」の境界線~実務の注意点を解説~
法人税2026年1月8日税務調査で狙われる「交際費」の境界線~実務の注意点を解説~ 仕事の考え方や価値観2025年12月28日科学的に証明された「やる気」の出し方。堀田秀吾著『すごい習慣大百科』から学ぶ行動の技術
仕事の考え方や価値観2025年12月28日科学的に証明された「やる気」の出し方。堀田秀吾著『すごい習慣大百科』から学ぶ行動の技術 消費税2025年12月23日インボイス途中登録者の消費税判定|特例を使える「基準期間売上」は税込・税抜どっち?
消費税2025年12月23日インボイス途中登録者の消費税判定|特例を使える「基準期間売上」は税込・税抜どっち?